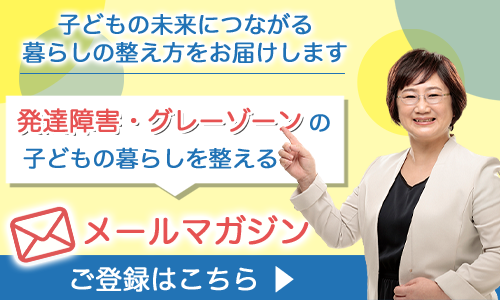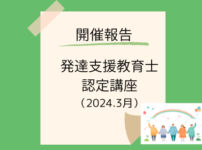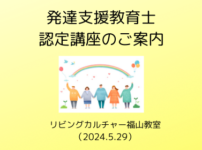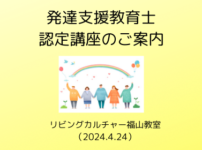整理収納で身につく3つの力
整理収納には
・時間的効果
・経済的効果
・精神的効果
という、3つの効果があると学びますが、子どもの整理収納では自立につながる3つの力を育てることができます。

1.おもちゃの整理を通して身につく「選ぶ力」
「選ぶ力」とは、自分にとって必要なモノを選んだり、物事の優先順位を考えることができるようになる力です。
私たちは毎日いろんな何かを選びながら生きていますよね。
例えば
・着る服
・食べるモノ
・誰とどこへ行くか
・どんなテレビを見るか
・何時にお風呂に入り、何時に寝るか
という日常的なものから
・卒業後の進路
・働き方はどうするか
・結婚するかどうかやパートナーは誰にするか
・どこに住むか
・子供はどうするか
など、人生においての大きな選択まで様々です。
これらの選択を自分以外の誰かに決めてもらうのではなくて、自分で考えて自分で決めることができるようになるために必要なのが「選ぶ力」です。
そしておもちゃの整理をするときに、子ども自身が考えて自分が遊んでいるおもちゃや自分にとって大事なおもちゃを選ぶことで「選ぶ練習」をすることができます。
だからこそ、大人が代わりに整理するのではなくて子ども自身に考えるチャンスをあげて欲しいと思っています。
そして自分で考えて選んだモノを大人が受け入れてくれることで、子どもの「選ぶ力」はぐんぐん育ちます。
2.収納を考えることで身につく「想像する力」
収納を考えるときに
・これはどんな時に使うだろう?
・これはどこで使うかな?
なども一緒に考えることによって「想像する力」が身につくようになります。
最初はうまくいかなくて、考えた収納が思ったより使いにくいということがあるかもしれません。
でも、その経験を重ねることで自分にとって出し入れしやすい収納とはどんな収納か?ということが分かるようになってきます。
自分が出し入れしやすい収納を考えるということは「少し先のことを考える」ことに繋がります。
例えばその日の予定に合わせて荷物を準備したりすることもできるようになってきます。
私の長男は大学進学のときに県外で一人暮らしを始めましたが、この力のおかげで
・引っ越し先の部屋を決める
・引っ越し先で使う家具や日用品を選ぶ
・引っ越しの荷造りをする
という、引越しに関わる準備をほとんど自分一人ですることができました。
さすがに引越し当日の作業は夫が手伝いましたが、私はお金を出すだけで他はほとんどノータッチでした。
出番がなくて寂しいという気持ちもありましたが、それ以上に自分でやり遂げた長男を誇りに思っています。
3.使ったら戻すことで身につく「続ける力」
「何かを使ったら元の場所に戻す」
一見簡単なことのようですが、いつもより疲れているときなどはつい後回しにしてしまうものです。
後回しが悪いわけではないのですが、それが続くとやがて部屋が乱れ、片付けることが面倒くさくなってしまいます。
そうならないためにも週に1回まとめて片付けるより、毎日少しずつ片付ける方がよっぽど楽なんですよね。
そして毎日「使ったら戻す」を繰り返すことで、決まったことを「続ける力」が身に付き、毎日の勉強やスポーツの練習などでも役に立ちます。
面倒くさいな…と思っても、1日5分片付けてみるだけでも全然違いますのでね。
子どもがちゃんと「使ったモノを元の場所に戻す」ことができるように、手助けをしてあげてくださいね。
整理収納で子どもの自立に必要な3つの力を見につけるために
- おもちゃの整理を通して身につく「選ぶ力」
- 収納を考えることで身につく「想像する力」
- 使ったら戻すことで身につく「続ける力」
この3つの力が子どもの自立に大切だということは分かったけど、じゃあどうしたらいいの?という話なのですが、おもちゃの整理も収納を考えるときも主役は子どもです。
おもちゃの整理をするときは
「あなたの好きなおもちゃはどれかな?」
「どのおもちゃで遊ぶのが楽しい?」
といった感じに聞きながら子どもが好きなおもちゃを選んでもらうことが大事です。
そしておもちゃの収納を考えるときは
「このおもちゃはどこで遊ぶ?」
「どんなふうに片付けると面倒くさくないかな?」
などと話し合いながら収納を考えてみましょう。
そして収納が決まったら「使ったら戻す」を繰り返します。
最初はうまくいかなくて片付けに時間がかかったり「捨てなきゃよかった」と思うことがあるかもしれません。
もし「捨てなきゃよかった」と思うことがあったとしても、それも子どもにとっては大事な経験です。
「いい経験になったね」とだけ言って、一緒にがっかりしたり子どもを責めたりしないようにしてくださいね。
選ぶ力
想像する力
続ける力
整理収納で身につく3つの力を身につけた子どもは、自立に向かって大きく成長してくれることと思います。