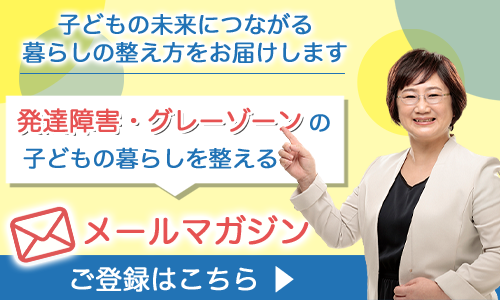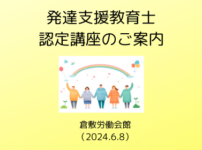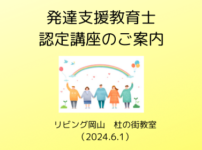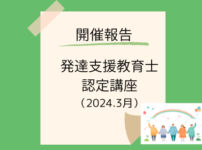「発達障害のある子どもは片付けられなくても仕方がありませんか?」という質問をいただきました。
「発達障害があるから片付けができない」と思われがちですが、決してそうではありません。
例えばSNS映えするような収納に片付けるのは難しいかもしれませんが、その子に合った収納やコミュニケーションを工夫すれば片付けられるようになることも多いです。
基本的に片付けとは使ったモノを元の場所に戻すことです。
つまり自分が使ったモノを元の場所に戻せるようになればいいということなんですね。
発達障害のある子どもの片付けはモノは少なく、収納は目で見て分かるようにするというのが基本ですが、それ以外に子どもの困りごとに対する支援も必要です。
子どもが困っていることを知る
子どもにとって大事なモノ・必要なモノを選ぶ
子どもが目で見て分かるように収納する
この3つを意識しながら、発達障害の子どもでも片付けやすい環境を整えていきましょう。
発達障害の子どもが片付けで困っていること
日常生活で発達障害の子どもが困っていることはいろいろありますが、片付けに関する困り事で言えば大きく次の3つに分けられます。
気が散りやすく、片付けの途中で忘れたり飽きたりしてしまう
こだわりが強い、気持ちの切り替えが苦手で片付けに取りかかれない
想像することや先を見通すことが苦手で片付けられない
それぞれどんな工夫をすればいいのでしょうか。

気が散りやすい子どもへの対応のポイント
片付けている途中で他のおもちゃに気をとられてしまう子どもには、集中できそうな時間をタイマーにセットして「これが鳴るまで片付けを頑張ろうね」と伝えてみましょう。
といってもいきなりすぐにできるようにはなりませんが「できなくても仕方がない、できたらラッキー」くらいの気持ちで見守って、できたときは目一杯ほめてあげてくださいね。
まずは「自分でできた」という経験を積み重ねることが大事です。
また、おもちゃの整理をするときなどは言葉で質問するよりも紙などに「遊んでいる」「遊んでいない」と書いて、そこにおもちゃを置いてもらうと分かりやすいです。
(文字が読めない子にはイラストやマークでも構いませんので子どもが理解できる表現にしてあげてください。)
気持ちの切り替えが苦手で片付けに取りかかれない子どもへの対応のポイント
こだわりの強い子どもにとって、遊んでいる途中に突然「片付けて!」と言われてもすぐには対応することは難しいです。
あらかじめ片付けのタイミング(ご飯の前や寝る前など)をイラストなどを使って説明しておき、片付ける時間が近づいたら「そろそろ片付けの時間だよ」と言いながら様子をみましょう。
強引に片付けさせようとしても逆効果なので、片付けのタイミングをルーティーン化するように日々の暮らしの中に片付けのタイミングを組み込むことが大事です。
その場合も言葉で伝えるだけじゃなく、イラストなどを使って1日の流れが分かるようにしておくと目で見て確認ができるので伝わりやすくなりますよ。
そして収納につけるラベルはこだわりが強すぎるとラベルの通りじゃないと嫌がる場合があり、片付けに時間がかかって嫌になる恐れがあります。
シンプルすぎるのもよくないですが、細かすぎても逆効果になるので「どんなラベルが一番子どもに負担なく伝わるか」ということを考えてあげてくださいね。
想像することが苦手な子供には具体的な表現で伝える
想像することが苦手な子供の場合
「片付けて」
「元の場所に戻して」
などの言い方では伝わらないことがあります。
その場合は
「このおもちゃを〇〇の絵が書いてあるカゴの中に入れてね。」
のように具体的に伝えてください。
他にも
「もう少しで片付けるよ」→「あと〇分で片付けるよ」
「ちゃんと片付けて」→「全部中に入れてね」
「そこに置いて」→「あの棚の〇〇の印の場所に置いてね」
など、言いかえるだけで伝わりやすい表現になる場面はたくさんあります。
普段何気なく使っている言葉が子どもに伝わりにくい表現になっている場合もありますのでね。
できるだけ具体的に、短い言葉で伝えるようにしてくださいね。
発達障害のある子どもの片付けの合言葉は「スモールステップ」
発達障害は脳の発達の偏りが原因と言われています。
そのため本人の努力だけでどうにかなることばかりではありません。
発達障害のある子どもが片付けられるようになるために大事なのは子どものペースに合わせることです。
できないことを探して怒るのではなくて、1つできるようになったらたくさんほめて次のステップへ進む、これがスモールステップのポイントです。
このようにできることから1つずつ進み、1段ずつ階段を上がるようにできるようになっっていったらいいのではないでしょうか。
そのためには「子どもが何に困っているのか」を知り、どうやったらその困っていることが軽減できるかを考えながら支援することが大事です。
そして「モノは少なく、収納は目で見て分かるように」を意識して、発達障害のある子どもでも片付けやすい環境を作ってあげてくださいね。