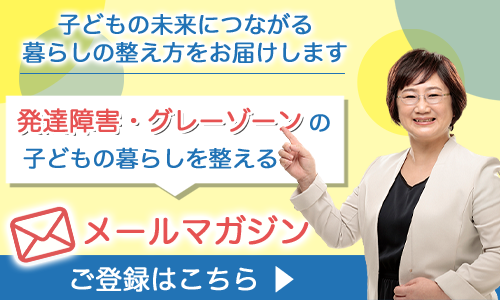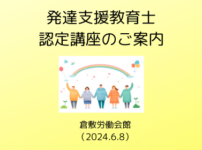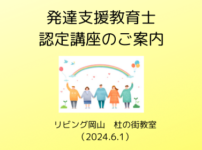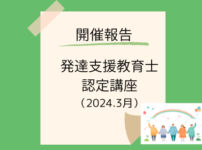子どもが片付けやすいようにとおもちゃの整理をして収納を整えたあと、忘れられがちなのが「ラベル」です。

ラベルとは?
収納の中に何が入っているかを示したシールやカードのこと。
モノを収納した場所にラベルを付けることを「ラベリング」といいます。
ラベルがあればどこに何があるかがすぐに分かるので、モノの出し入れをするのにとても便利なのですが
・面倒くさい
・後でやろうと思って忘れる
・子どもが分かっているから大丈夫だと思っている
などという理由で「付けなくてもいいかな」と思ってしまいがちなのも事実です。
でも、私は片付けが苦手な人や子どものおもちゃの収納にこそ、ラベルはあった方がいいと思っています。
ラベルはなぜ必要なのか?
ラベルの役目は「どこに何があるかが目で見て分かる」ようにすることです。
どこに何があるかが目で見て分かれば、遊びたいおもちゃがすぐに見つかりますし、片付けるときもどこに片付けたらいいかがすぐに分かるので片付けるのが楽になります。
でも「後でやろう」と思うと日常の忙しさについ忘れがちですよね。
だからこそ収納を整えたらすぐにラベルを付けて欲しいのです。
ラベルを付けることに慣れてないと「いちいちラベルを付けるのは面倒くさい」と思うかもしれません。
実は面倒くさいのは最初だけ。一度ラベルを付ければ、後は収納を変更したときだけ付け替えればいいので、それほど面倒でもありません。
今は100円ショップに「一度貼っても簡単にはがせるラベルシール」という商品もありますし、簡単なメモ程度でもいいのでね。
収納を整えたらすぐに中に何が入っているか分かるようにしてあげてくださいね。
ラベルを付けるのは誰のため?
おもちゃの収納の場合「そのおもちゃで遊ぶ子どもが分かっているからラベルがなくても大丈夫」と思うかもしれません。
でも、子どもの友達や祖父母、親戚の子どもなどが遊びにきたときはどうでしょうか?
他の人には分からないからと自分の子どもだけで片付けてもらうのは、片付ける子どもも納得できないでしょう。
だからといって片付けるときに「これはどこに片付けるの?」と聞かれてばかりでは答える方も面倒になりますよね。
私は長男が幼稚園のときに「長男が分かっているからいいか」と思っておもちゃの収納にラベルを付けていませんでした。
(というか「ラベルを付ける」こと自体を考えてもいませんでした)
そして「分からなかったら聞いてもらえばいいし」とも思っていたのですが、これが大失敗。
というのも、毎回片付けのたびに「これはどこー?」「分からんから片付けん!」などというやり取りをしていて、楽どころかかなり面倒くさかったのです。
(長男は友達を家に招くのが好きで、当時は週に3回は誰かが遊びに来ていたのです)
そして友達が元々の場所とは違うところに片付けると長男が「そこじゃない!」と注意して、友達は「わざわざ片付けたのに!」とケンカになる…
当時は「なんでこんなことになるんだろう?」と頭を抱えていました。
でも、幼稚園の保育室ですべてのおもちゃの置き場所がイラストとひらがなで子どもでも分かるように書いてあるのを見て「これだ!」と思いましてね。
すぐにマネをしておもちゃの置き場所に「何が入っているか」を書きました。
その結果「どこに片付けたらいいか分からない」という理由でのトラブルは激減です。
たかがラベル、されどラベル
最初は面倒くさいと思うかもしれませんが、片付けの負担が少なくなることを思えば付けない理由はありません。
ラベルを作るときのポイント
子どものおもちゃの収納にラベルをつけるときは「子どもが目で見て分かるように」してあげてください。
どういうことか?というと
例えば収納に「積み木」が入っている場合
・TSUMIKI
・積み木
・ツミキ
・つみき
・積み木のイラスト
・積み木の写真
など、いろんなラベルの書き方があります。
書き方によっては何が書いてあるか分からない場合があり、せっかくラベルをつけても子どもが書いてある内容を理解できなかったら意味がありません。
そして同じおもちゃでも、大人と子どもとでは違う言葉で認識している可能性があるので注意が必要です。
例えば
・大人は「レゴ」だと思っていても子どもは「ブロック」だと思っている
・大人は「リカちゃん」だと思っていても子どもは「にんぎょう」だと思っている
・大人は「プリンセス」だと思っていても子どもは「おひめさま」だと思っている
などなど。
(我が家では長男は「たたかい」次男は「へんしん」だと思っていたおもちゃがありました。)
せっかくおもちゃの収納にラベルを付けても、子どもに伝わらないと意味がありません。
「どんな風に書いたら分かるかな?」と子どもに聞きながら、一緒にラベルを作ってみてくださいね。
子どもと一緒に考えたラベルは、それだけでも子どもの片付けのやる気を引き出してくれますよ。