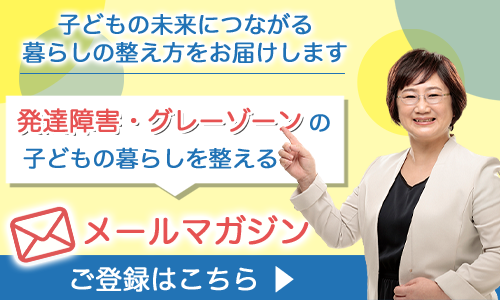子どもに片付けられるようになってほしい親心
子どもに片付けられるようになって欲しい
毎日コツコツじゃなくて、今!すぐに片付けられるようになる方法ってないの?
そう思う方は、少なくないのではないでしょうか。
子どもが片付けられるようになれば、毎日「片付けなさい!」と怒らなくてすむのでイライラしなくていいですし、子どもが片付けてくれている間に他の家事ができるととっても助かりますよね。
だからこそ、1日でも、いや1秒でも早く片付けられるようになって欲しいと思うのは自然なことだと思います。
ただ…残念ながら、1日2日で子どもが片付けられるようになるか?と聞かれると私の答えは「NO」です。
なぜなら片付けは「技術×習慣」で身につくものだから。
つまり子どもが自分に合った片付け方を知り、毎日片付けることによって身につくものだからです。
そして子どもが自分に合った片付け方を知るためには「なぜ子どもは片付けられないのか?」を知る必要があります。
子どもが片付けられない理由
子どもが片付けられない理由は3つあります。
・おもちゃの量が多くて片付けの負担になっている
・おもちゃの収納が子どもに合っていない
・どうやって片付けたらいいか分かっていない
順番にご説明しましょう。
おもちゃの量が多くて片付けの負担になっている
おもちゃの量が多ければ多いほど、片付けの負担も増えます。
そのため「おもちゃの量が多くて片付けられない」のであれば、おもちゃを減らすしかありません。
といっても、「捨てる」という意味ではないですよ。
まずは子どものスペースに収納するのは子どもが無理なく片付けられる量だけにして、残りは別の場所で保管するだけでも大丈夫です。
そしてもし減らせないのであれば、増やさないことも大事です。
例えば外出先などでおもちゃを見れば子どもは「欲しい」と思いますが、その後の片付けのことまでは考えてはいないことがほとんどです。
それにいくら買う前に「買ったらちゃんと片付けるんだよ」と約束しておもちゃを買っても、実際に片付けてみないとできるかどうかは分からないものです。
だから片付けない子どもに「片付けるって言うから買ったのに!」と怒っても仕方のないことなんですよね。
おもちゃの量が多いかどうかを子ども自身で考えることは難しいです。
だからこそ、時々一緒にチェックしてあげてくださいね。
おもちゃの収納が子どもに合っていない
おもちゃの置き場所を決めていて、それぞれの置き場所にラベルをつけているのに子どもが片付けない場合はおもちゃの収納が子どもに合っていない可能性があります。
収納にフタがついているだけで面倒くさいと思ったり、カゴに入れることすら嫌だと思う子どももいますのでね。
収納を整えたのに子どもが片付けない場合は「どこか片付けにくいところがあるのかな?」と考えてみてくださいね。
どうやって片付けたらいいか分かっていない
こう書くと「え?毎日片付けてるのに分からないってなぜ?」と思いませんか?
確かに毎日片付けていれば「子どもも片付け方が分かっているだろう」と思うのも無理はありません。
以前ある小学生の女の子と話をしたとき
「片付けなさいって言われるといつもその辺に突っ込んでるの。それじゃあダメなの?」
と質問されたことがありました。
本人も何か違和感を感じていたから質問してきたのでしょう。
だって「突っ込んでる」って、自分で言っちゃってますからね。
基本的に片付けとは「使ったモノを元の場所に戻すこと」です。
そのため部屋に散らかっているモノを「適当に空いているスペースに突っ込む」という行為は片付けとは言えません。
それぞれの置き場所を決めて、使ったらその場所に戻すことが大事です。
そう説明すると納得したようでした。
でも、それでその女の子が片付けができるようになるかは別の問題です。
なぜなら「元の場所」を作る作業をしなくては「元に戻す」ことはできないからです。
そのため「まずはお家の人と一緒におもちゃの置き場所を考えてみてね」と伝えました。
片付けの負担にならないおもちゃの量
子どもが片付けやすい収納
子どもに合った片付け方を教える
子どもが片付けられるようになるためにはこの3つが大切です。
そして「教えたからすぐにできるようになる」のではなくて、毎日の積み重ねが大事なのです。
千里の道も一歩から。
どうか長い目で見守ってあげてくださいね。