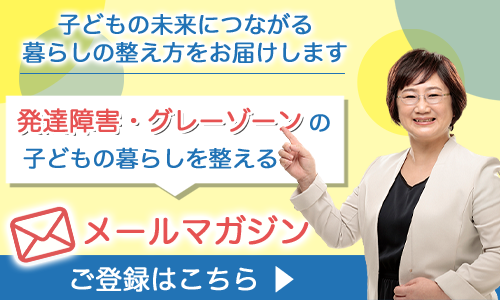おもちゃの量を人と比べて不安になったことはありませんか?
「うちはおもちゃが少ないんじゃないか?」と、不安になったことはありませんか?
子どもが小さくて他の家と比べる機会がないときは、そんなことを思わなかったのに
・子どもの友達の家に行ったらたくさんのおもちゃがあるのを見た
・遊びに来た子どもの友達に「これだけしかないの?」と言われた
など、他の家のおもちゃ事情を知るとつい比べてしまうことがあるかもしれません。
特に子どもの友達に「これだけしかないの?」なんて言われた日には、恥かしいやら悔しいやら…
どうやって気持ちを落ち着けようかとモヤモヤしたのは、過去の私です。
だけど安心してください。
大事なのは「たくさんのおもちゃがあること」ではありません。
(極端に制限して、少なすぎる場合は別として)
おもちゃが少ないからといって、その子どもがかわいそうということはありませんよ。

子どもの話を聞いてみよう
おもちゃの量が少ないと言われたとき、あなたの子どもはどう思ったのでしょうか。
「別に平気だよ」という子どももいるかもしれませんし、「恥ずかしいと思った」「たくさんのおもちゃがあるお友達がうらやましいと思った」など、いろんな気持ちがあると思います。
おもちゃが少なくて恥ずかしいと思った、お友達がうらやましいからといって、すぐに新しいおもちゃを増やす必要はなくて、まずは子どもの気持ちを受け止めてあげてください。
大切な話はその後から始めたって遅くはありません。
ちょうどいいおもちゃの量とは
基本的にちょうどいいおもちゃの量とは子どもが1人で無理なく片付けられる量です。
そして子どもが集中できる時間は
・未就学の子どもであれば年齢×1~1.5分以内
・小学生以上であれば10分以内
と言われていることから、その時間内に片付けられる量がその子にとってちょうどいいおもちゃの量だと思っていただければ分かりやすいのではないでしょうか。
そして量よりもっと大事なのはおもちゃの質です。
といっても、流行りのおもちゃや高いおもちゃがいいという話じゃないですよ。
・子どもが本当に気に入っているおもちゃ
・いつも楽しそうに遊んでいるおもちゃ
などがその子にとっての「質のいいおもちゃ」です。
これは流行りのおもちゃや高いおもちゃが悪いという話ではなくて、「子どもが気に入っているかどうか」を基準にしてくださいという話です。
(流行りのおもちゃも時には必要ですからね)
それにたくさんのおもちゃに囲まれているより、適量のおもちゃがある方が子どもの集中力が育つと言われています。
だからこそ
「外出先でねだられたから」とか
「みんなが持っているから」とか
などの理由で増やすのではなくて、おもちゃを増やすときは慎重になって欲しいと思っています。
とはいえ「本当に必要なのかどうか?」ということを子どもが判断するのは難しいでしょう。
だからまずは子ども自身が「自分にとってちょうどいいおもちゃの量」を知ることが大事なのです。
そしてその「自分にとってちょうどいいおもちゃの量」の範囲内で「増えたら減らす」を繰り返すように教えてあげてください。
慣れてきたら自分で判断できるようになってきますよ。
周りの意見より大切なこと
実は私の長男がまだ小さかったときに「うちって貧乏なん?」と聞いてきたことがありました。
突然なんでそんなことを聞くのかと思って話を聞いてみたところ、遊びに来た友達が「おもちゃが少ないから、おまえの家は貧乏だ」と言ったらしいのです。
当時の長男は「貧乏」という言葉の意味が分からなかったために聞いてきたらしいのですが、私は恥ずかしいというより「おもちゃの数だけでそんなことを言われることが悔しい」と思いました。
そこで長男に簡単に「貧乏とは?」ということについて説明した後「自分はどう思う?」と聞いてみたのです。
すると「うーん…オレは別に困ってないしなぁ…よく分からんし、どっちでもいい」という答えが返ってきました。
つまり「貧乏」という言葉の意味が知りたかっただけで「自分が貧乏かどうか」というのはあまり気にしていなかったみたいでした。
私はつい長男も恥ずかしいとか悔しいと感じていたのかと思っていたので「なんだ、そうだったのか」と拍子抜けしたのを覚えています。
このとき「自分が納得していれば、周りの意見は気にしなくてもいいんだ」ということを、長男に教えてもらいました。
まとめ
子どもの行動範囲が広がりいろんな友達と交流するようになると、いろいろと比べることがでてくるのは自然なことです。
とはいえおもちゃの量が多いとか少ないとかという話は、他の人と比べてすぐに分かるものではありません。
そしてもちろん「おもちゃが少ないと子どもがかわいそう」ということもありません。
・まずは子どもが無理なく片付けられる量を知ること
・そしてその量を維持できるように「増えたら減らす」ことができること
この2つの方が大事です。
「よそはよそ、うちはうち」という言葉があるように、他の家の事情に影響されすぎないように、子どもと話し合ってみてくださいね。